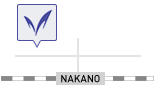- HOME
- > セミナー・イベント一覧
- > 共同利用・共同研究拠点 MIMS「現象数理学研究拠点」共同研究集会
共同研究拠点・研究集会
2023年度:新型コロナウイルス感染症に関する対応について
明治大学は、2023年4月1日からの春学期開始に合わせて、「明治大学活動制限指針レベル」を「レベル1」から「レベル0」に引き下げています。昨年度まで大学として講じていた各種の感染拡大防止策は、4月1日から5月7日までの「移行期間」を経て、順次、緩和しています。
〇4月1日以降のマスク着用の考え方について
政府は、2023年3月13日以降、マスク着用の考え方を見直し、マスク着用は個人の判断に委ねることを基本とする旨の方針を公表しています。また、この方針について、学校への適用は2023年4月1日以降とされたことを受け、本学も同日以降、マスクの着用を求めないことを基本としています。ただし、政府の方針で、混雑した電車に乗車する際等、状況に応じてマスクの着用が推奨されています。本学においても状況に応じて、マスクの着用を推奨する場合があるため、その際は、各自、適切な判断をお願いします。
共同利用・共同研究拠点
MIMS 現象数理学研究拠点 共同研究集会
2023年度
| 採択一覧 | 2023年度開催 |
|---|---|
| 主催 | 共同利用・共同研究拠点 明治大学先端数理科学インスティテュート(MIMS) 「現象数理学拠点」 |
| 中野キャンパスへのアクセス | |
| 募集要項 | |
| これまでの 開催記録 |
|
2023年度開催
研究集会型「経費支援タイプ」
| 2023年 7月21日-22日 |
中田 聡 (広島大学) |
|
|---|---|---|
| 9月1日-2日 | 田中美栄子 (明治大学) |
|
| 9月12日-13日 | 島 弘幸 (山梨大学) |
|
| 12月8日-9日 | 藤江 遼 (神奈川大学) |
|
| 12月15日-16日 | 奈良知惠 (明治大学) |
|
| 2024年1月 26日–27日 |
北畑裕之 (千葉大学) |
Complex motile matter - from single agents to collective behaviors
- 日時 | Date
- 2023年7月21日(金)、22日(土)/ July 21st (Fri.) and 22nd (Sat.), 2023.
- 場所 | Venue
対面参加 明治大学中野キャンパス 6階研究セミナー室
On-site Meiji University Nakano Campus 6F Seminar room
オンライン参加
On-line participation
※ 事前登録制。
概要
生命現象を数理的、物理的に理解しようとする研究は様々なステージで進められている。例えば、細胞内の複雑な反応ネットワークを詳細に解析したり、細胞運動を解析したり、さらには個体レベルや群レベルのダイナミクスを観測したりしている。本研究集会では、これらの数理生物学・生物物理学の分野から、理論研究と実験研究をバランスよく講演者を集め、現在の最先端のトピックを共有するとともに、異なる分野の研究者同士で情報交換することで新たな研究の方向性を探ることを目的とする。
組織委員 | Organizing Committee
| 中田聡(広島大学) | Satoshi Nakata (Hiroshima Univ.) |
| 北畑裕之(千葉大学) | Hiroyuki Kitahata (Chiba Univ.) |
| Carsten Beta (ポツダム大学、金沢大学) | Carsten Beta (Univ. of Potsdam, Kanazawa Univ.) |
| 末松 J. 信彦(明治大学) | Nobuhiko J. Suematsu (Meiji Univ.) |
| 板谷昌輝 (ブダペスト工科経済大学) | Masaki Itatani (Budapest University of Technology and Economics) |
参加登録 | Registration
申し込みフォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください。
Please click the "Registration" buttons to open the registration form.
終了しました
Closed
Program
講演は全て英語で行われます。
lectures will be given in English.
| July 21st (Fri.) | |
|---|---|
| 12:50 - 13:00 | Opening |
Chair: Hiroyuki Kitahata (Chiba University) |
| 13:00 - 13:45 | Kei Fujiwara (Keio University) "Behaviors and characteristics of intracellular Reaction-diffusion wave revealed by a reconstitution system in artificial cells" |
|---|---|
| 13:45 - 14:30 | Natsuhiko Yoshinaga (Tohoku University) "Reaction-diffusion models for Min oscillations: wave instability in a confined space" |
| 14:30 - 14:45 | break |
Chair: TBA |
| 14:45 - 15:30 | Satoshi Sawai (The University of Tokyo) "Cell-cell contact mediated regulation of cell polarity and collective movement" |
|---|---|
| 15:30 - 16:15 | Masatoshi Ichikawa (Kyoto University) "Self-propelled droplets: from model system to living cell" |
| 16:15 - 16:30 | break |
Chair: Carsten Beta (University of Potsdam, Kanazawa University) |
| 16:30 - 17:05 | Muneyuki Matsuo (The University of Tokyo) "Supramolecular recursion due to complex motility" |
|---|---|
| 17:05 - 17:40 | Masaki Itatani (Budapest University of Technology and Economics) "Design of transient pH oscillations utilizing a combination of two antagonistic enzymatic reactions and implementing it to synthetic cells" |
| July 22nd (Sat.) |
|
|---|
Chair: Nobuhiko J. Suematsu (Meiji University) |
| 10:00 - 10:45 | Akihiro Isomura (Kyoto University) "Illuminating oscillatory gene expression in cell-cell communications" |
|---|---|
| 10:45 - 11:30 | Shuji Ishihara (The University of Tokyo) "Onset of pattern propagation on curved surfaces" |
| 11:30 - 13:00 | Lunch |
Chair: Satoshi Nakata (Hiroshima University) |
| 13:00 - 13:45 | Carsten Beta (University of Potsdam, Kanazawa University) "Hybrid active matter – how motile cells actuate passive micro-cargo" |
|---|---|
| 13:45 - 14:30 | Akira Kakugo (Kyoto University) "Implementation of transport tasks by Active Matter" |
| 14:30 - 14:40 | Closing |
This workshop is supported by MEXT Joint Usage/Research Center Meiji University "Center for Mathematical Modeling and Applications" (CMMA).
Data-driven Mathematical Science:
経済物理学とその周辺 2023
- 日時
- 2023年9月1日(金)、2日(土)
- 場所
- 明治大学中野キャンパス 6階研究セミナー室
概要
Econophysicsという名で、経済と社会の仕組みを物理学的・情報科学的手法で解明することを目指し、日本物理学会の会員と進化経済学会の会員の一部を主体とする境界領域の開拓を目指す研究グループによる研究発表の会合として、数年前より明治大学数理科学インスティテュート「現象数理学研究拠点」の支援を得て明治大学中野キャンパスで開催してきた。過去3年間はcovid-19の影響で遠隔開催やハイブリッド開催となったが、2023年度は対面開催ができる運びとなった。今年度は9月1日午後から2日にかけての1日半の開催となる。東京圏に居住する、水野(国立情報研)、黒田(明治学院大)、家富(立正大)、前野(明治大)、金子(国際基督教大)、増川(成城大)、荻林(千葉工大)等と北陸圏に居住する、石川(金沢学院大)、藤本(金沢学院大)、および京都圏に居住する、田中(明治大)、有賀(中央大)、金澤(京大)等、および九州圏の石崎(福岡県大)等が対面して意見交換できる貴重な機会として機能している。加えて本研究会の発表論文を主体とした英文論文集を来春にSpringerからの出版を目指して投稿査読中である。
組織委員
田中美栄子(明治大学) 、家富 洋(立正大学)、石川 温(金沢学院大学)
藤本祥二(金沢学院大学)、水野貴之(国立情報学研究所)、乾 孝治(明治大学)
黒田正明(明治大学/明治学院大学)、守 真太朗(弘前大学)
Program
| 9月1日(金) | |
|---|---|
| 12:30-13:30 | 荻林成章(千葉工業大学) |
| 13:30-14:30 | 家富 洋(立正大学) |
| 14:30-15:00 | 田中美栄子(明治大学) |
| 15:00-15:30 | 名倉 賢(大和大学) |
| 15:30-16:30 | 増川純一(成城大学) |
| 16:30-17:30 | 前野義晴(明治大学) |
| 9月2日(土) | |
|---|---|
| 10:00-11:00 | 金子拓也(国際基督教大学) |
| 11:00-12:00 | 石川 温(金沢学院大学) |
| 12:00-13:00 | 昼休憩 |
| 13:00-14:00 | 藤本祥二(金沢学院大学) |
| 14:00-15:00 | 水野貴之(国立情報学研究所) |
| 15:00-16:00 | 石崎龍二(福岡県立大学) |
| 16:00-17:00 | 有賀裕二(中央大学) |
植物の「カタチ」と「チカラ」を解き明かす 2023
- 日時
- 2023年9月12日(火)、13日(水)
- 場所
- 明治大学中野キャンパス 6階研究セミナー室
概要
公園の樹木から花壇の花々、さらには道ばたの雑草にいたるまで、私たちの周りは多種多様なカタチをした植物であふれています。この研究会では、こうした植物の形態と構造に注目し、組織レベルで発揮される植物の力学的性質がいかに優れているのかを、現象数理学の視点から明らかにすることを目指します。
分子生物学が発達した今日では、すべての植物の生理作用が、遺伝子レベル・細胞レベルで緻密に制御されていることがわかっています。しかし本研究会では、その一つ上の階層である「植物の組織レベル」(例えば樹木の幹・枝・葉・根など)に注目します。植物組織の形態およびそこに作用する各種のチカラ(重力・曲げ応力・膨圧・摩擦力など)は、絶妙な釣り合いを保ちながら、時々刻々と変化する環境条件に適応しているはずです。こうした植物のカタチとチカラが織りなす機能美に対して、数理科学・工学・生物学をまたぐ学際的な視点からの議論を行います。
組織委員
島 弘幸(山梨大学),山口智彦(明治大学)
Program
★印は招待講演
| 9月12日(火) | |
|---|---|
| 12:50-13:00 | ごあいさつと各種アナウンス |
| 13:00-13:45 | ★ 和田 浩史 (立命館大学) |
| 13:45-14:30 | ★ 北沢 美帆 (大阪大学) |
| 14:30-14:45 | 休憩 |
| 14:45-15:30 | ★ 樋口 裕美子 (東京大学) |
| 15:30-16:15 | ★ 中益 朗子 (明治大学) |
| 16:15-16:45 | 学生・院生によるショートトーク 2件 |
| 9月13日(水) | |
|---|---|
| 10:00-10:45 | ★ 南光 一樹 (森林総合研究所) |
| 10:45-11:15 | 小野田 雄介 (京都大学) |
| 11:15-11:45 | 金浜 瞳也 (北海道大学) |
| 12:00-13:30 | 昼休憩 |
| 13:30-14:15 | ★ 谷垣 健一 (大阪電気通信大学) |
| 14:15-14:45 | 石川 和也 (立命館大学) |
| 14:45-15:15 | 学生・院生によるショートトーク 2件 |
| 15:15-16:00 | 解散 (フリーディスカッション) |
社会物理学とその周辺
- 日時
- 2023年12月8日(金)、9日(土)
- 場所
- 明治大学中野キャンパス 6階研究セミナー室3
概要
「社会物理学」は、物理学の視点・方法(特に統計物理学の手法)に基づき、社会性をもつ集団の示す様々な現象を理解するための取り扱い方を確立し、社会現象に潜む普遍的法則の解明を目指す学問である。研究対象は、格差社会の発生、都市の発達と形状、意見形成、文化・言語の進化、暴動、感染症・情報の流布など多岐に渡り、さらにその範囲を広げている。またインターネットの急速な普及、SNSなどの新しいコミュニケーションの発達、購買行動データの蓄積等により、人や社会のダイナミクスが実証可能になりつつある。しかし、広範な研究対象を扱う方法論は発展途上であり、また、数理モデルに代表される理論的研究とデータ解析などの実証的研究が互いに交流し協働する場が少ないのが現状である。本研究集会では、多岐に渡る社会物理学の研究を対象として、モデルの構築とシミュレーションによって普遍性を探求する理論研究、実データの解析から社会現象に見られる法則を検証する実証研究を目指す研究者が情報交換する場を提供する。
組織委員
藤江 遼(神奈川大学)、小田垣孝(科学教育総合研究所株式会社)、山崎義弘(早稲田大学)
山本 健(琉球大学)、佐野幸恵(筑波大学)、田中美栄子(明治大学)、守 真太郎(弘前大学)
國仲寛人(三重大学)、石崎龍二(福岡県立大学)、渡邊隼史(成城大学)、西森 拓(明治大学)
田村義保(統計数理研究所)、佐藤彰洋(横浜市立大学)、黒田正明(明治学院大学)
森史(九州大学)、石川 温(金沢学院大学)、松下 貢(中央大学)、前野義晴(明治大学)
高石哲弥(広島経済大学)、飯沼邦彦(RGAリインシュアランスカンパニー)
Program
| 12月8日(金) | |
|---|---|
| 13:00-13:05 | はじめに |
| 13:05-13:50 | 前野義晴 (明治大学) |
| 13:50-14:35 | 柴田加菜子(明治大学),岡田勇(創価大学) |
| 14:35-15:20 | 家富洋,相馬亘(立正大学) |
| 15:20-15:30 | 休憩 |
| 15:30-16:15 | 須田礼二(グリーンエネルギーサイト) |
| 16:15-17:00 | 水口毅(大阪公立大学),鈴木岳人(青山学院大学) |
| 17:00-17:45 | 中石海,吉田遼,梶川康平,福島孝治,大関洋平(東京大学) |
| 12月9日(土) | |
|---|---|
| 10:00-10:45 | 久門正人(野村證券株式会社),中山一昭(信州大学),守真太郎(弘前大学) |
| 10:45-11:30 | 石崎龍二(福岡県立大学),福島和洋(熊本大学),井上政義(鹿児島大学) |
| 11:30-12:15 | Abhijit Chakraborty(Kyoto University),Tetsuo Hatsuda(RIKEN iTHEMS),Yuichi Ikeda(Kyoto University) |
| 12:15-13:15 | 昼休憩 |
| 13:15-14:00 | 後藤大尭,白石允梓,西森拓(明治大学) |
| 14:00-14:45 | 藤本悠雅(総合研究大学院大学) |
| 14:45-15:30 | 全卓樹(高知工科大学) |
| 15:30 | 閉会 |
折り紙の科学を基盤とするアート・数理および
工学への応用Ⅳ
- 日時
- 2023年12月15日(金)、16日(土)
- 場所
- 明治大学中野キャンパス 高層棟6階603
12月15日午前の部 ハイブリッド形式
組織委員、講演者のみ対面/オンライン視聴公開(Zoom Webinar)・事前登録制。
12月15日午後の部、16日 現地(対面)参加のみ。申込不要。※ オンラインはありません。
ただし、ワークショップは事前登録制。
概要
折り紙の科学は数理・情報・工学・機械・建築・医療・芸術・教育等と広範囲の分野に拡大し続けています 。そこで、特に、「折り紙のアート・数理」および「折紙工学」をキーワードに、関連する分野の研究者が横断型に研究交流する場として、15日の午前の部は(オンラインを主とする)ハイブリッド方式で、15日の午後の部と16日は現地参加のみで開催します。
15日は” Handbook of Discrete and Computational Geometry”の編集者かつ” Geometric Folding Algorithms”の著者でもあるJoseph O’Rourke教授による特別招待講演でスタートします。本研究集会では最新の研究成果の情報ばかりでなく、折り紙作家の前川淳氏など種々の分野の研究者による講演を用意しました。また、16日には折り紙作家として世界的に活躍中の布施知子氏によるワークショップも実施します。折り紙の科学が日々の暮らしとの接点をさらに広め発展する一助となれば幸いです。
組織委員
奈良知惠(NARA Chie, Chair)(明治大学)、萩原一郎 (HAGIWARA Ichiro)(明治大学)
上原隆平(UEHARA Ryuhei)(JAIST)、三谷 純(MITANI Jun)(筑波大学)
舘 知宏(TACHI Tomohiro)(東京大学)、西森拓(NISHIMORI Hiraku)(明治大学)
開催方法
12月15日午前の部 ハイブリッド形式
組織委員、講演者のみ対面/オンライン視聴公開(Zoom Webinar)・事前登録制。
12月15日午後の部、16日 現地(対面)参加のみ。※ オンラインはありません。
ただし、ワークショップは事前登録制。
視聴参加申込
(主催者からの招待参加者の方は、申し込み不要です。)
◆ 12月15日午前の部 ハイブリッド形式。オンライン視聴(Zoom Webinar)事前登録。
視聴参加登録申込フォーム
↓ ↓終了しました
◆ 12月15日午後の部、16日 現地(対面)参加のみ。申込不要。※ オンラインはありません。
ただし、ワークショップは事前登録制。
ワークショップ参加申し込みフォーム ※締め切りは12月7日です。
↓ ↓終了しました
Program
| 12月15日(金) 午前の部 | ◆ オンライン公開 |
|---|---|
| 9:50-10:00 | 開会(Opening) |
| 10:00-11:00 |
特別招待講演(Special invited talk): Joseph O’Rourke (Smith College) |
| 11:00–11:15 | 休憩 |
| 11:15–11:45 |
斉藤一哉(Kazuya Saito, 九州大学) |
| 11:45-12:00 |
山崎桂子 (Keiko Yamazaki, 明治大学) |
| 12:00–12:15 |
佐々木淑恵 (Toshie Sasaki, 明治大学) |
| 12:15–12:45 |
松原和樹 (Kazuki Matsubara, 埼玉大学) |
| 12:45-14:15 | 昼休憩 |
| 12月15日(金) 午後の部 | ◆ 対面開催:明治大学中野キャンパス 高層棟6階603 (オンラインはありません。) |
|---|---|
| 14:15-14:45 |
上原隆平 (Ryuhei Uehara, JAIST) |
| 14:45–15:00 |
阿部 綾 (Aya Abe, 明治大学) |
| 15:00–15:30 |
伊藤大雄 (Hiro Ito, 電気通信大学) |
| 15:30–16:00 |
前川 淳 (Jun Maekawa, 折り紙作家) |
| 16:00-16:15 | 休憩 |
| 16:15-16:45 |
寺田耕輔 (Kosuke Terada, 明星大学) |
| 16:45-17:15 |
舘 知宏 (Tomohiro Tachi, 東京大学) |
| 12月16日(土) | ◆ 対面開催:明治大学中野キャンパス 高層棟6階603 (オンラインはありません。) |
|---|---|
| 10:00-10:30 |
三谷 純 (Jun Mitani, 筑波大学) |
| 10:30-11:00 |
村井紘子 (Hiroko Murai, 奈良女子大学) |
| 11:00-11:30 |
賈 伊陽 (Yiyang Jia, 成蹊大学) |
| 11:30-12:30 |
ワークショップ:布施知子 (Tomoko Fuse, 折り紙作家) |
| 12:30-14:00 | 昼休憩 |
| 14:00-14:30 |
ルイス ディアゴ (Luis D. Diago, 明治大学) |
| 14:30-15:00 |
萩原一郎 (Ichiro Hagiwara, 明治大学) |
| 15:00-15:30 |
堀山貴史 (Takashi Horiyama, 北海道大学) |
| 15:30-15:45 | 休憩 |
| 15:45-16:15 |
宮本好信 (Yoshinobu Miyamoto, 愛知工業大学) |
| 16:15-16:45 |
安田博実 (Hiromi Yasuda, JAXA) |
| 16:45-17:15 |
奈良知惠 (Chie Nara, 明治大学) |
| 17:15-17:25 | 閉会(Closing) |
アクティブマター研究会2024
Active Matter Workshop 2024
- 日時 | Date
- January 26 (Fri) and 27 (Sat), 2024.
- 場所 | Venue
- 明治大学中野キャンパス 6階研究セミナー室1.2.3
Meiji University Nakano Campus 6F Seminar room1, room2, room3
Overview / 概要
We are pleased to announce that the Active Matter Workshop 2024 will be held on January 26 and 27, 2024. There are three invited lectures. In addition, there is an opportunity for participants to give contributed oral presentations and poster presentations on all fields of active matter. The workshop is planned to be held in an on-site format at Meiji University (Nakano campus). The deadline for the abstract submission for contributed oral and poster presentations is Dec. 31, 2023. The deadline for registration for participants without presentation is Jan. 19, 2024. See below for the details of registration and abstract submission.
All the presentations will be given in English.
非平衡条件下で自由エネルギーを散逸することにより自発的に運動する素子やその集団が自律的に秩序を生み出す系はアクティブマターと呼ばれ、近年盛んに研究されている。アクティブマターは学際的な研究領域であり、物理学だけにとどまらず、応用数学、化学、生物学、工学などさまざまな分野の研究者が参画してきている。このような学際的な研究分野であるアクティブマターに関して、国内外から様々な研究者が集まり、議論することは、アクティブマターの分野の発展に大きく貢献できる。そこで、本研究会では、3件の招待講演と一般申込みによる短時間の講演14件を行い、アクティブマターの研究の今後の方向性を探る。
組織委員 / Organising committee
研究代表者:北畑裕之(千葉大学) KITAHATA Hiroyuki (Chiba Univ.)
江端宏之(九州大学) Hiroyuki Ebata (Kyushu Univ.)
末松 J 信彦(明治大学) Nobuhiko J. Suematsu (Meiji Univ.)
多羅間充輔(九州大学) Mitsusuke Tarama (Kyushu Univ.)
Invited lectures
|
Akira Kakugo (Kyoto University) |
|
Michiko Shimokawa (Nara Woman's University) |
|
Shuichi Nakamura (Tohoku University) |
Program
| [Day1] 2024/1/26 | |
|---|---|
| 9:40 –10:00 | Registration |
| 10:00 –10:05 | Opening |
| Chair: | Tarama |
| 10:10 –11:00 | [PL] Shimokawa, Michiko (Nara Woman’s University) "Bifurcation of Rotational Motion of Elliptical Camphor Coated Disk" |
| 11:00 –11:20 | Break |
| Chair: | Shimokawa, Michiko |
| 11:20 –11:40 | Tanaka, Shinpei "Diffusion-reaction-advection equation for a self-propelled droplets system driven by a sink of surfactants" |
| 11:40 –12:00 | Hatatani, Miku "Spinning symmetric gear driven by chiral surface wettability on a vibrating water bed" |
| 12:00 –13:30 | Lunch |
| Chair: | Tanaka, Shinpei |
| 13:30 –14:20 | [PL] Nakamura, Shuichi (Tohoku University) "Mechanism and biological significance of flagella-dependent bacterial motility" |
| 14:20 –14:40 | Break |
| Chair: | Nakamura, Shuichi |
| 14:40 –15:00 | Tarama, Mitsusuke "Microphase separation of actin cytoskeleton during tubulogenesis" |
| 15:00 –15:20 | Yasuda, Kento "Entropy change due to stochastic state transitions of odd Langevin system" |
| 15:20 –15:40 | Kitahata, Hiroyuki "Spontaneous motion of an oil droplet coupled with deformation into a crescent shape" |
| 15:40 –16:10 | Break |
| Chair: | Yasuda, Kento |
| 16:10 –16:30 | Matsukiyo, Hiroki "Oscillating Edge Current in Polar Active Fluid" |
| 16:30 –16:50 | Ichikawa, Masatoshi "Measurement of rheotaxis of ciliates" |
| 16:50 –17:10 | Hosaka, Yuto "Lorentz Reciprocal Theorem in Fluids with Odd Viscosity" |
| 17:10 –17:30 | Ebata, Hiroyuki "Effective temperature-dependent rheology of living cell cytoplasm" |
| 18:00 – | General discussion/ Banquet |
| [Day2] 2024/1/27 | |
|---|---|
| Chair: | Ichikawa, Masatoshi |
| 9:30 – 9:50 | Adachi, Kyosuke "Power-law correlation of polarity in simple active matter models" |
| 9:50 –10:10 | Matsuura, Kaito "Geometric frustration and pairing order transition in confined bacterial vortices" |
| 10:10 –10:30 | Kuroda, Yuta "Long-range translational order and hyperuniformity in twodimensional chiral active crystal" |
| 10:30 –10:50 | Break |
| Chair: | Kakugo, Akira |
| 10:50 –11:10 | Yoshii, Kiwamu "Glassy behavior in active deformable particle model" |
| 11:10 –11:30 | Molina, John "Bayesian Machine Learning for Soft Matter Flows" |
| 11:30 –13:00 | Lunch |
| 13:00 –14:30 | Poster |
| 14:30 –14:40 | Break |
| Chair: | Molina, John |
| 14:40 –15:30 | [PL] Kakugo, Akira (Kyoto University) "Cooperative task achievement found in active-matter" |
| 15:30 –15:40 | Closing |
Presentation time
Plenary lectures (PL) [50 min each, including discussions]
Contributed presentations [20 min presentation, including discussions]
Poster list
| 1. Azuma, Shogo “Anomalous diffusion and turbulence of chiral active matter” |
| 2. Iwanaga, Taiga “Flow and jamming of confined active Brownian particles” |
| 3. Hosono, Shota “Linear Stability of Active Chiral Nematics with Friction” |
| 4. Gong, Yiming “Construction of a physical reservoir computing device using active matter made from a swarm of biomolecular motors” |
| 5. Araya, Yuki “Synchronization of oscillatory flows in two coupled collapsible tubes” |
| 6. Hayano, Haruki “Anomalous rheology of active suspensions” |
| 7. Mallick, Rony “A membrane-covered active droplet: Effect of liquid membrane of polydimethylsiloxane on run-and-chase motion between droplets of 1-decanol and ethyl salicylate” |
| 8. Dam, Duc “Unjamming and fluidization of active Brownian particles” |
| 9. Hakuta, Shinya “Laser induced self-generated and self-propelled multicomponent droplets” |
| 10. Nakayama, Bokusui “Self-pioneering Janus Particles in a Temperature-responsive Polymer Solution” |
| 11. Kaneko, Kojiro “Simulation of self-propelled rods restricted by curved geometries” |
| 12. Naya, Masayuki “Photo-excited micro-droplet robotics” |
| 13. Tateyama, Yuta “Bifurcation analysis of pattern dynamics in non-reciprocal Swift-Hohenberg model” |
| 14. Nimphius, Phillip “Deterministic Active Particles in a Two-Dimensional Harmonic Potential” |
Presentation
Odd numbers → 13:00 - 13:45
Even numbers → 13:45 - 14:30
Tips for poster presentations
1. The size of the poster board is 960 mm in width and 1800 mm in hight.
2. The recommended size of your poster is ISO A0 (841 mm × 1189 mm).
Registration
To attend the workshop, registration is required also for participants without presentation.
To attend the workshop with a presentation, please finish the registration and abstract submission by 2023/12/31 (Sun) (See above).
To attend the workshop without presentation, please finish the registration by 2024/1/19 (Fri) from the link below.
Please feel free to contact the organising committee if you have any questions.
Links to the registration page and the abstract template
Closed
Organiser
MEXT Joint Usage/Research Center Meiji University "Center for Mathematical Modeling and Applications" (CMMA)
Co-organiser
2023年度開催
研究集会型「独立開催タイプ」
| 2023年 7月3日 |
井上雅世 (九州工業大学) |
|
|---|---|---|
| 2024年 3月4日-5日 |
第18回 錯覚ワークショップ |
杉原厚吉 (明治大学) |
| 3月25日 | 数理の現状と課題 |
萩原一郎 (明治大学) |
現象数理学のダイバーシティ
- 日時
- 2023年7月3日(月)
- 開催
- オンライン開催(Zoom:Webinar機能利用)※事前申込制
概要
現象数理学の対象は、社会、自然、生命など多岐にわたる。これらの現象の解明には、俯瞰的な視点も重要であるものの、同じ現象を扱っている異分野との交流や共同研究はハードルが高いのが現状である。そこで本研究会では、現象数理学と深く関連する、社会物理学、非線形科学、デザイン学、心理学、数理生物学、データ科学といった様々な分野の研究者を招き議論する機会を設けることで、文理融合を含めた学際的な共同研究の可能性を模索する。加えて、キャリアに関するフリーディスカッションを開催し、自然科学分野におけるダイバーシティについて議論する。
組織委員
井上雅世(九州工業大学)、大谷智子(大阪芸術大学)、北沢美帆(大阪大学)、西森 拓(明治大学)
- 開催方法
- Zoom Webinar使用。オンラインで開催
- 参加申込:事前登録制
- ※ 主催者からの招待参加者の方は、申し込み不要です。
専用申し込みフォーム
↓ 終了しました
Program
| 9:50-10:00 | Opening |
|---|---|
| 10:00-10:30 | 佐野幸恵(筑波大学) |
| 10:30-11:00 | 小澤歩(東京大学) |
| 11:10-11:40 | 小串典子(大阪大学) |
| 11:50-13:30 | 昼休憩&フリーディスカッション |
| 13:40-14:10 | 大谷智子(大阪芸術大学) |
| 14:10-14:40 | 木塚あゆみ(大阪芸術大学) |
| 14:40-15:00 | 休憩 |
| 15:00-15:30 | 陰山真矢(関西学院大学) |
| 15:30-16:00 | 藤原真奈(京都大学/広島大学) |
| 16:10-16:40 | 北沢美帆(大阪大学) |
| 16:40-16:50 | 総括 |
錯覚の創作・モデリング・解明とその応用展開
第18回錯覚ワークショップ
- 日時
- 2024年3月4日(月)、5日(火)
- 場所
- 明治大学中野キャンパス 6階研究セミナー室
組織委員長
杉原厚吉(明治大学)
組織委員
宮下芳明(明治大学)、北岡明佳(立命館大学)、一川 誠(千葉大学)、谷中一寿(神奈川工科大学)
星加民雄(錯視アーティスト)、近藤信太郎(岐阜大学)、須志田隆道(サレジオ工業高等専門学校)
大谷智子(大阪芸術大学)、山口智彦(明治大学)
概要
今年度の「錯覚ワークショップ」を明治大学中野キャンパスにおいて対面で開催します。今年度の中心テーマは「錯覚の創作・モデリング・解明とその応用展開」ですが、これに限らず錯覚に関する研究発表を広く募り、この分野の研究者の交流の場を提供します。ふるってご参加ください。
- 研究発表の募集
締め切りました
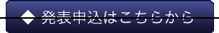
| スケジュール | |
| 2024年 1月15日(月) | 発表申し込みの締め切り |
| 1月22日(月) | 採否の連絡 |
| 2月9日(金) | アブストラクト(A4判1ページ)の締め切り |
| 3月4日(月)、5日(火) | 錯覚ワークショップ |
プログラム
| 3月4日(月) | |
|---|---|
| 13:00~13:40 | 間瀬実郎(呉工業高等専門学校) |
| 13:40~14:20 | 長谷川能三 |
| 14:20~15:00 | 一川誠(千葉大学) |
| 15:00~15:20 | 休憩 |
| 15:20~16:00 | 宮地夏希、谷中一寿*(神奈川工科大学) |
| 16:00~16:40 | 森川和則(大阪大学) |
| 3月5日(火) | |
|---|---|
| 9:00~9:40 | 西本博之(実験経営学研究所) |
| 9:40~10:20 | 杉原厚吉(明治大学) |
| 10:20~10:40 | 休憩 |
| 10:40~11:20 | 石川将也(コグ) |
| 11:20~11:40 | 古賀理則*、井上雅世(九州工業大学) |
| 11:40~13:30 | 昼休憩 |
| 13:30~14:10 | 北岡明佳(立命館大学) |
| 14:10~14:50 | 星加民雄(錯視アーティスト) |
| 14:50~15:10 | 休憩 |
| 15:10~15:50 | 田谷修一郎(慶応義塾大学) |
| 15:50~16:30 | 臼井健太郎*(立命館大学)、石川将也(コグ)、田谷修一郎(慶応義塾大学)、北岡明佳(立命館大学) |
(*印は、複数著者の場合の講演者)
◆ 会場の隣室で、講演の一部について関連展示も予定しています。◆
- 主催
- 明治大学「現象数理学」共同利用・共同研究拠点
- 共催
- 明治大学研究ブランディング事業「数理科学する明治大学」(第2期)錯覚・錯視チーム
科研費基盤研究(B)
「自然環境下での奥行き錯視の数理モデル構築と事故防止・知育教育への応用」
科研費挑戦的研究(萌芽)
「『超不可能立体』の発掘とその錯視誘発要因の定量化・体系化」
- 連絡先
- 第18回錯覚ワークショップ組織委員長 杉原厚吉
kokichis[a]meiji.ac.jp ([a]を@におき替えてください。)
高度な自動運転を実現するための数理の現状と課題
- 日時
- 2024年3月25日(月)
- 開催
- オンライン開催(Zoom:Webinar機能利用)
概要
明治大学MIAD(先端科学ELSI研究所(旧名称:自動運転社会総合研究所)では、令和2年度から始まった「対馬スマートシティー事業」を昨年9月で終了させた。永平寺の磁力線埋め込みタイプ、境町の高精度三次元地図利用タイプに対し、世界に先駆け「隠れトレースライン」の創出と有効性を示した。これにより自動運転の初期及び維持費用の大幅な低減の可能性を示した。本シンポジウムでは、来るべき実装の準備として次のことを議論する場とする。
1)「隠れトレースライン」の現状と課題
2)Maas(Mobility as a Service)の現状と課題
3)車々間通信の現状と課題
4)自動運転社会の未来像
5)ドライブシミュレーターの自動運転走行技術への応用
6)交通流シミュレーターの自動運転走行技術開発への応用
7)自動運転技術への制御技術、機械学習、折紙工学の貢献
組織委員
萩原一郎(明治大学)、内田博志(明治大学)、藤井秀樹(東京大学)
古川 修(電動モビリティシステム専門職大学)、岡村 宏(芝浦工業大学)
ディアゴ・ルイス(明治大学)、安部博枝(明治大学)、西森 拓(明治大学)
開催方法
Zoom Webinar使用。オンラインで開催
参加申込:事前登録制
※ 主催者からの招待参加者の方は、申し込み不要です。
専用申し込みフォーム
↓ 終了しました
プログラム
| 3月25日(月) | |
|---|---|
| 11:00~11:30 | 萩原一郎(明治大学) |
| 11:30~12:00 | 長谷川浩志(芝浦工業大学) |
| 13:30~14:00 | 岡村宏(芝浦工業大学) |
| 14:00~14:30 | 古川修(電動モビリティシステム専門職大学) |
| 14:30~15:00 | 滝川桂一(明治大学) |
| 15:00~15:30 | 福島正夫((株)三技協) |
| 15:40~16:10 | ディアゴ・ルイス(明治大学) |
| 16:10~16:40 | 藤井秀樹(東京大学)
|
| 16:40~17:10 | 内田博志(明治大学) |
| 17:10~17:40 | 総合討論 |
2023年度開催
共同研究型「独立開催タイプ」
| 2024年 3月15日 |
扇構造の工学的芸術的アプローチ |
萩原一郎 (明治大学) |
|---|
折紙構造・折紙式プリンター・扇構造の
工学的芸術的アプローチ
- 日時
- 2024年3月15日(金)
- 開催
- オンライン開催
概要
共同研究型で実施する。日頃から次の課題で共同研究を実施している。
1) 折紙構造音響室
2) 折紙構造エネルギー吸収部材
3) 折畳み扇構造
4) 折紙安全輸送箱
5) 切り紙ハニカム
6) 因果の分かる機械学習
7) エネルギー最適制御
これらのテーマでは、それぞれ共同研究者は異なるが、打ち破るべき解析技術の開発の主たるポイントは共通している。そこで上記の各共同研究者が集まり、共通する技術の開発を行う。
組織委員
萩原一郎(明治大学)、内田博志(明治大学)、寺田耕輔(明星大学)
趙 希禄(埼玉工業大学)、奈良知恵(明治大学)、ルイスディアゴ(明治大学)
戸倉 直((株)トクラシミュレーションリサーチ)西森 拓(明治大学)
開催方法
Zoom Webinar使用。オンラインで開催
参加申込:事前登録制
※ 主催者からの招待参加者の方は、申し込み不要です。
専用申し込みフォーム
↓ 終了しました
プログラム
3月15日(金) 10:00~10:10 萩原一郎(明治大学)
開催趣旨10:10~11:20 山崎桂子(明治大学)
「閉じた折畳音響室」
萩原一郎(明治大学)
「FreeFEMへ組み込むべき高精度・高効率解析技術」
佐々木淑恵(明治大学)
「IEDT変更法による固有周波数制御」
阿部綾(明治大学)
「IEDT変更法によるトラックキャビンへの適用」
追記 IEDT(Interactive Energy Density Topology)の略
11:20~12:00 討議
岡村宏(芝浦工業大学)、吉村卓也(都立大学)、松本敏郎(名古屋大学)
石濱正男(明治大学)、橋口真宜、米大海(計測エンジニアリングシステム(株))、 安達悠子(明治大学)13:30~14:00 佐々木淑恵、ディアゴ・ルイス、萩原一郎(明治大学)
「お洒落なヘルメットの衝撃特性」14:00~14:30 討議
寺田耕輔(明星大学)、戸倉直(トクラシミュレーションリサーチ(株))
篠田淳一((株)インターローカス)14:30~15:00 ディアゴ・ルイス、萩原一郎(明治大学)
「扇の現状と今後」15:00~15:30 討議
奈良知惠(明治大学)、武笠雅子((株)スペースシーファイブ)
安達悠子(明治大学)、黒澤英考(江戸伝統工芸・芸術文化保存振興協会)
篠田淳一((株)インターローカス)15:30~16:00 ディアゴ・ルイス、安達悠子(明治大学)
「蛇腹折りの自動化など扇の製作法」16:00~16:30 討議
黒澤英考(江戸伝統工芸・芸術文化保存振興協会)
岩瀬将美(東京電機大学)、内田博志(明治大学)
篠田淳一((株)インターローカス)16:30~16:40 閉会の挨拶