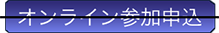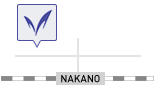- HOME
- > セミナー・イベント一覧
- > 共同利用・共同研究拠点 MIMS「現象数理学研究拠点」共同研究集会
共同研究拠点・研究集会
共同利用・共同研究拠点
MIMS 現象数理学研究拠点 共同研究集会
2025年度
| 採択一覧 | 2025年度開催 |
|---|---|
| 主催 | 共同利用・共同研究拠点 明治大学先端数理科学インスティテュート(MIMS) 「現象数理学拠点」 |
| 中野キャンパスへのアクセス | |
| 募集要項 | |
| これまでの 開催記録 |
|
2025年度開催
研究集会型「経費支援タイプ」
| 2025年 9月26日 |
守 真太郎 (弘前大学) |
|
|---|---|---|
| 11月14日 | 大谷 智子 (大阪芸術大学) |
|
| 12月8日–9日 | 藤江 遼 (九州大学) |
|
| 12月11日–12日 | 奈良 知惠 (明治大学) |
|
| 2026年 1月23日–24日 |
北畑 裕之 (千葉大学) |
|
| 3月2日–3日 | (第20回錯覚ワークショップ) |
杉原厚吉 (明治大学) |
| 3月18日 | 萩原 一郎 (明治大学) |
2025年度開催
研究集会型「独立開催タイプ」
| 2026年 3月6日 |
石森洋行 (国立環境研究所) |
|---|
2025年度開催
共同研究型「独立開催タイプ」
| 2026年 3月5日 |
銀河の力学構造の解明に向けての数理的研究 |
神部 勉 (明治大学) |
|---|
Data-driven mathematical Sciences:
経済物理学とその周辺
- 日時
- 2025年9月26日(金)
- ハイブリッド開催
対面参加 明治大学中野キャンパス研究セミナー室3
オンライン参加
概要
経済物理学(Econophysics)は、物理学の手法を用いて経済・金融現象を解析する学際的研究分野として発展してきました。近年では、データ駆動型アプローチの重要性が高まり、機械学習やAIの進展により、計算手法やモデリング技術が大きく進化しています。本研究集会では、Data-driven Mathematical Sciences の視点から、以下のようなトピックに関する研究発表と議論を行います。
- ● 金融市場のビッグデータ解析:高頻度取引データの統計分析、価格変動の確率過程モデル、情報流の影響
- ● 機械学習を用いた市場予測:ディープラーニング、強化学習、生成モデルによる経済・金融データ解析
- ● ネットワーク科学と経済ダイナミクス:企業間取引ネットワーク、金融ネットワークの安定性、システミックリスク評価
- ● エージェントベース・モデリング(ABM):個々の意思決定が市場に与える影響のシミュレーション、経済政策評価
- ● 進化経済学・行動経済学との統合:異種エージェントモデル、行動バイアスを考慮した市場ダイナミクスの再現
本研究集会を通じて、データ駆動型手法の応用が経済物理学にもたらす可能性を探り、経済・金融分野における数理科学の発展と学際的連携の促進を目指します。
オンライン参加申込
専用申し込みフォーム
↓ 終了しました
組織委員
研究代表者: 守真太朗(弘前大学)
田中美栄子(金沢学院大学)、石川 温(金沢学院大学)、有賀裕二(京都先端科学大学)
石崎龍二(福岡県立大学)、増川純一(成城大学)、藤本祥二(金沢学院大学)
家富 洋(立正大学)、水野貴之(国立情報学研究所)、西森 拓(明治大学)
Program
| 9:30–9:35 | 開会挨拶 |
|---|---|
セッション1 |
座長:守 真太郎(弘前大学理工学研究科) |
| 9:35–9:50 | 菅原知弥(大阪大学基礎工学研究科システム創成専攻)、守 真太郎(弘前大学理工学研究科) |
| 9:50–10:05 | 清水太陽、守 真太郎(弘前大学理工学研究科) |
| 10:05–10:15 | 高森大聡、守 真太郎(弘前大学理工学研究科) |
| 10:15–10:40 | 久門正人(野村証券) |
| 10:40–10:45 | 休憩 |
セッション2 |
座長:田中美栄子(金沢学院大学情報工学部) |
| 10:45–11:10 | 高橋友則(総合研究大学院大学)、水野貴之(国立情報学研究所) |
| 11:10–11:20 | 王菲(総合研究大学院大学)、水野貴之(国立情報学研究所) |
| 11:20–11:30 | 水野貴之(国立情報学研究所)、中嶋一貴(東京都立大学) |
| 11:30–11:55 | 水野貴之(国立情報学研究所) |
| 12:00-13:00 | 昼休憩 |
セッション3 |
座長:水野貴之(国立情報学研究所) |
| 13:00–13:20 | 後藤弘光(金沢学院大学)、相馬亘(立正大学) |
| 13:20–13:35 | WU QIANYUN(東京科学大学情報理工学院)、佐野幸恵(筑波大学システム情報系)、高安秀樹(東京科学大学情報理工学院)、Havlin Shlomo(Bar-Ilan University Department of Physics)、高安美佐子(東京科学大学情報理工学院) |
| 13:35–13:50 | 藤原俊太、佐藤優輝、金澤輝代士(京都大学) |
| 13:50–14:05 | ジャン ジウェイ(東京科学大学情報理工学院) |
| 14:05–14:15 | 結城実怜、相馬 亘(立正大学データサイエンス学部) |
| 14:15–14:25 | 休憩 |
セッション4 |
座長:増川純一(成城大学経済学部) |
| 14:25–14:50 | 相馬 亘(立正大学データサイエンス学部), Carolina Magna Roma (Brazilian Development Bank), Irena Vodenska (Boston University) |
| 14:50–15:10 | 石崎龍二(福岡県立大学)、井上政義(鹿児島大学名誉教授) |
| 15:10–15:30 | 有賀裕二(京都先端科学大学) |
| 15:30–15:55 | 石川 温(金沢学院大学情報工学部) |
| 15:55–16:05 | 石川 温(金沢学院大学情報工学部) |
| 16:05–16:15 | 休憩 |
セッション5 |
座長:石川 温(金沢学院大学情報工学部) |
| 16:15–16:40 | 増川純一(成城大学経済学部) |
| 16:40–17:00 | 佐野幸恵(筑波大学システム情報系) |
| 17:00–17:10 | 万 李陽(筑波大学大学院システム情報工学研究群)、武内 慎(サイバーエージェント)、森下壮一郎(サイバーエージェント)、佐野幸恵(筑波大学システム情報系) |
| 17:10–17:30 | 田中美栄子(金沢学院大情報工学部) |
| 17:30–17:35 | 閉会挨拶:田中美栄子(金沢学院大学) |
現象数理学のダイバーシティ'25
- 日時
- 2025年11月14日(金)
- ハイブリッド開催
対面参加 明治大学中野キャンパス6階研究セミナー室3
オンライン参加
概要
現象数理学は、社会・自然・生命など多様な現象を対象とする学際的分野である。本研究集会では、メディア論、データサイエンス、心理科学、数理生物学、非線形物理学など関連分野の研究者を招き、分野横断的な議論を通じて文理を越えた新たな共同研究の可能性を探る。
今年度は新たに「現象」を主題とするアーティストを迎え、アートと数理の融合を意識したセッションを実施する。科学とは異なる視点から現象をとらえる営みは、多様性=ダイバーシティを象徴するものであり、本集会の大きな特色となる。
さらに、キャリアやダイバーシティを自由に語り合う場も継続し、多様な分野の研究者が対話と連携を深める機会を創出する。
オンライン参加申込
専用申し込みフォーム
↓ 終了しました
組織委員
研究代表者:
大谷智子(大阪芸術大学)
井上雅世(九州工業大学)、阿部綾(明治大学)、北沢美帆(大阪大学)、西森拓(明治大学)
Program
| 10:05–10:15 | オープニング |
|---|---|
| 10:30~ | 賈伊陽 (東京都市大学) |
| 11:00~ | 村井紘子(奈良女子大学) |
| 11:30~ | 昼休み&フリーディスカッション |
| 13:00~ | 坂下美咲(東京理科大学) |
| 13:30~ | 林智子 (大阪芸術大学) |
| 14:00~ | ワークショップ(予定) |
| 15:00~ | 質疑応答&フリーディスカッション |
| 16:0 0 | クロージング |
社会物理学とその周辺
- 日時
- 2025年12月8日(月)、9日(火)
- ハイブリッド開催
対面参加 明治大学中野キャンパス6階研究セミナー室3
オンライン参加
概要
社会物理学は、物理学の視点・手法を用いて人の社会行動や社会現象の理解を目指した研究領域である。本研究集会では、社会現象を扱う研究者による講演と討論を予定しており、社会物理学の方向性や解決すべき問題についても議論する。また社会学や生物学などの研究者にも参加を募り、多角的な議論を行うことで社会物理学の方向性を模索する。また、一般からの発表も募集する。
組織委員
研究代表者:藤江遼(九州大学)
小田垣孝(科学教育総合研究所株式会社)、山崎義弘(早稲田大学)
山本健(琉球大学)、佐野幸恵(筑波大学)、田中美栄子(金沢学院大学)
守真太郎(弘前大学)、石崎龍二(福岡県立大学)、西森拓(明治大学)
佐藤彰洋(横浜市立大学)、黒田正明(明治学院大学)
森史(九州大学)、石川温(金沢学院大学)、前野義晴(明治大学)
高石哲弥(広島経済大学)、渡邊隼史(成城大学)
講演発表の募集
講演者を募集しております。講演ご希望の方は、2025年11月6日(木)までにご登録ください。
講演は次の申込フォームでお申込みください。
↓ ↓締め切りました
オンライン視聴申込
Zoomで聴講希望の方は以下よりご登録ください(後日、Zoomの招待リンクをお送りします)
Zoom参加申込は次の申込フォームでお申込みください。
↓ ↓終了しました
※ 対面参加の場合は登録不要です。当日、会場でご記帳ください。
Program
| 12月8日(月) | |
|---|---|
| 10:30-10:40 | はじめに |
| 10:40-11:10 | 久門正人(野村證券),守真太郎(弘前大学) |
| 11:10-11:40 | 山本健(琉球大学) |
| 11:40-12:10 | 藤江遼(九州大学) |
| 12:10-13:00 | 昼休憩 |
| 13:00-13:30 | 阪上雅昭(京都大学),野中哲士(神戸大学) |
| 13:30-14:00 | 中村秀規(富山県立大学),藤江遼(九州大学) |
| 14:00-14:30 | 石川温(金沢学院大学),藤本祥二(金沢学院大学),水野貴之(国立情報学研究所) |
| 14:30-15:00 | 佐野幸恵(筑波大学),園田一貴(筑波大学),藤宮仁(ダイナコム),鳥居寛之(東京大学),宇野 賀津子(ルイ・パストゥール医学研究センター) |
| 15:00-15:10 | 休憩 |
| 15:10-16:10 | 【招待講演】笹原和俊(東京科学大学) |
| 16:10-17:00 | 総合討論 |
| 12月9日(火) | |
|---|---|
| 10:30-11:00 | 石崎龍二(福岡県立大学) |
| 11:00-11:30 | 藤田悠朔(大阪公立大学),鈴木岳人(高千穂大学),水口毅(大阪公立大学) |
| 11:30-12:00 | 中道晶香(京都産業大学),森川雅博(理化学研究所) |
| 12:00-12:30 | 森川雅博(理化学研究所),森川遥光(カリフォルニア州立大学LB),中道晶香(京都産業大学) |
| 12:30-13:30 | 昼休憩 |
| 13:30-14:00 | 若月大暉(京都大学),金澤輝代士(京都大学) |
| 14:00-14:30 | 貞政隆杜(大阪公立大学),水口毅(大阪公立大学) |
| 14:30-15:00 | 大泉嶺(国立社会保障・人口問題研究所) |
| 15:00-15:30 | 小田垣孝(科学教育総合研究所) |
| 15:30 | 閉会 |
折り紙の科学を基盤とするアート・数理および
折紙工学への応用(Ⅵ)
- 日時
- 2025年12月11日(木)、12日(金)
- 会場
- 明治大学中野キャンパス研究セミナー室3
概要
「折り紙のアート・数理」および「折紙工学」をキーワードに、関連する分野の研究者が横断型に研究交流する場として研究集会を対面式で開催します。本テーマで第6回目となり今年度は折り紙とロボティクスを結び付けて活躍する世界的エキスパートのDr. Matthew Gardiner氏(zoom 出演)を特別招待講演者にお迎えする運びとなりました。「折り紙の科学」が多様な研究基盤をどのように支えているか、質疑・応答などを通して理解・認識を深めて個々の研究や教育の一助となることを期待しています。
組織委員
研究代表者:
奈良知惠(明治大学)
上原隆平(JAIST), 三谷純(筑波大学), 舘知宏(東京大学)
萩原一郎(明治大学), 西森 拓 (明治大学)
Program
| 12月11日(木) | |
|---|---|
| 9:50-10:00 | 開会(Opening) |
| 10:00-10:30 | 杉原 厚吉 (Kokichi Sugihara, 明治大学) |
| 10:30-11:00 | 村井 紘子(Hiroko Murai, 奈良女子大学) |
| 11:00-11:30 | 賈 伊陽(Yiyang Jia, 東京都市大学) |
| 11:30-12:00 | 三谷 純 (Jun Mitani, 筑波大学) |
| 12:00-13:30 | ~昼休み |
| 13:30-13:45 | 山崎 桂子 (Keiko Yamazaki 明治大学) |
| 13:45-14:00 | 佐々木 淑恵 (Toshie Sasaki, 明治大学) |
| 14:00-14:30 | 伊藤 大雄 (Hiro Ito, 電気通信大学) |
| 14:30-15:00 | 宮本 好信(Yoshinobu Miyamoto, 愛知工業大学) |
| 15:00-15:30 | 舘 知宏(Tomohiro Tachi, 東京大学) |
| 15:30-16:00 | ~休憩 |
| 16:00-17:00 | 特別招待講演(Special invited talk): Dr. Matthew Gardiner (Head of Art Science Research Strategies / Futurelab, zoom) |
| 12月12日(金) | |
|---|---|
| 10:00-10:30 | 斉藤 一哉(Kazuya Saito, 九州大学) |
| 10:30-11:00 | 堀山 貴史 (Takashi Horiyama, 北海道大学) |
| 11:00-11:30 | ルイス ディアゴ (Luis Diago, 明治大学) |
| 11:30-11:45 | 篠木 啓佑 (Keisuke Shinoki, 明治大学) |
| 11:45-12:00 | 内田 京花 (Kyoka Uchida, 明治大学) |
| 12:00-12:15 | 杉山 有希子 (Yukiko Sugiyama, 明治大学) |
| 12:15-12:30 | 阿部 綾 (Aya Abe, 明治大学) |
| 12:30-14:00 | 昼休み |
| 14:00-14:30 | 上原 隆平(Ryuhei Uehara, JAIST) |
| 14:30-15:00 | 鎌田 斗南 (Tonan kamata, JAIST) |
| 15:00-15:30 | 松原 和樹 (Kazuki Matsubara, 埼玉大学) |
| 15:30-16:00 | 萩原 一郎 (Ichiro Hagiwara 明治大学) |
| 16:00-16:30 | 奈良 知惠 (Chie Nara, 明治大学) |
| 16:30-16:40 | 閉会(Closing) |
International Active Matter Workshop 2026
- 日時 | Date
- January 23 (Fri) and 24 (Sat), 2026
- 場所 | Venue
- 明治大学中野キャンパス
Meiji University Nakano Campus
Overview / 概要
We are pleased to announce that the International Active Matter Workshop 2025 will be held on January 23 and 24, 2026.
There are three invited lectures. In addition, there is an opportunity for participants to give contributed oral presentations and poster presentations on all fields of active matter.
The workshop is planned to be held in an on-site format at Meiji University (Nakano campus).
The deadline for the abstract submission for contributed oral and poster presentations is Dec. 19 (Fri), 2025.
The deadline for registration for participants without presentation is Jan. 12 (Mon), 2026.
See below for the details of registration and abstract submission.
All the presentations will be given in English.
自発的に運動を示すもの、あるいはそのようなものの集団を総称して、アクティブマターと呼びます。その具体的な対象は、我々人間を含む生物系とコロイド粒子などを用いた人工系の両方を含みます。例えば生命現象に着目すると、分子モーター、細胞、生体組織、個体、そして多数の個体が集まった「群れ」の運動などは全てがアクティブマターです。このように、アクティブマターは、ナノメートルスケールからメートルスケールまで様々な長さスケールで見つかります。また、その時間スケールも、秒単位から数日の単位まで、対象によっていろいろです。時間、空間ともに様々なスケールで見られる具体例の示すダイナミクスに共通する法則を明らかにしようとするのがアクティブマターの研究です。また、生物系と人工系の両方に見られる現象を同じ視点で論じることができるため、その背後に潜む普遍性が明らかになり、生命現象の理解が深まると期待されます。
様々なスケールにわたるこれらの多様な現象に共通するのは、これらが平衡から大きく外れた非平衡な状態にあると言うことです。このことは、アクティブマターが自ら運動エネルギーを生み出すことで「自発的に」運動することからも伺えます。同時に、アクティブマターは運動することによりエネルギーを散逸します。このようにアクティブマターは複雑な非平衡開放系です。その原理の理解は工学的応用の観点からも重要です。そのため、アクティブマターは、物理学、数学、化学、生物学、工学などの様々な分野で研究されています。
組織委員 / Organising committee
研究代表者:北畑裕之(千葉大学) Hiroyuki Kitahata (Chiba Univ.)
江端宏之(九州大学) Hiroyuki Ebata (Kyushu Univ.)
山本量一(京都大学) Ryoichi Yamamoto (Kyoto Univ.)
末松 J 信彦(明治大学) Nobuhiko J. Suematsu (Meiji Univ.)
多羅間充輔(九州大学) Mitsusuke Tarama (Kyushu Univ.)
John J. Molina(京都大学)
Important Dates
| Oct. 31, 2025 | Open for the registration and the abstract submission for contributed presentations |
| Dec. 19, 2025 | Deadline for the abstract submission for contributed oral and poster presentations |
| Jan. 12, 2026 | Deadline for participation without presentation |
| Jan. 23, 2026 | Active Matter Workshop 2026 (Day 1) |
| Jan. 24, 2026 | Active Matter Workshop 2026 (Day 2) |
Invited lectures
|
Katsuhiro Nishinari (University of Tokyo) |
|
Istvan Lagzi (Budapest University of Technology and Economics) |
|
Carsten Beta (University of Potsdam and Kanazawa University) |
Program
| 1/23 Fri | |
|---|---|
| 9:30- 9:50 | Registration |
| 9:50- 9:55 | Opening remark |
| 9:55-10:55 | Carsten Beta |
| 10:55-11:05 | Break |
| 11:05-11:25 | CT1 |
| 11:25-11:45 | CT2 |
| 11:45-13:00 | Lunch |
| 13:00-13:20 | CT3 |
| 13:20-13:40 | CT4 |
| 13:40-14:00 | CT5 |
| 14:00-14:20 | CT6 |
| 14:20-14:40 | CT7 |
| 14:40-15:00 | Group photo / Coffee break |
| 15:00-16:40 | Poster Presentations |
| 16:40-16:45 | Break |
| 16:45-17:45 | Istvan Lagzi |
| 18:00-20:00 | Social meeting |
| 1/24 Sat | |
|---|---|
| 9:30- 9:50 | Registration |
| 9:50-10:10 | CT8 |
| 10:10-10:30 | CT9 |
| 10:30-10:50 | CT10 |
| 10:50-11:10 | CT11 |
| 11:10-11:30 | Coffee break |
| 11:30-11:50 | CT12 |
| 11:50-12:10 | CT13 |
| 12:10-12:30 | CT14 |
| 12:30-13:30 | Lunch |
| 13:30-13:50 | CT15 |
| 13:50-14:10 | CT16 |
| 14:10-14:30 | CT17 |
| 14:30-14:50 | Coffee break |
| 14:50-15:50 | Katsuhiro Nishinari |
| 15:50-16:00 | Closing remark |
Invited lectures:60 min (including discussions)
Contributed Talks:20 min (including discussions)
Contributed Oral Presentations
We accept abstracts for contributed oral presentations (approx. 20 min each).
If you wish to give a contributed oral presentation, first finish the registration by 2025/12/19 (Fri) from the registration, during which you are asked to upload the PDF abstract file of your presentation. Note the size of the file should be less than 1 MB.
Please find the template below and prepare a pdf file with your name in the file name as "abstract_LastName_FirstName.pdf".
If the number of submissions exceeds the number of slots for contributed oral presentations, the speakers will be selected based on the abstracts. The submissions not selected as contributed oral presentations will be considered as contributed poster presentations.
Contributed Poster Presentations
We accept abstracts for contributed poster presentations.
If you wish to give a contributed poster presentation, finish the registration by 2025/12/19 (Fri) from the registration, during which you are asked to upload the PDF abstract file of your presentation. Note the size of the file should be less than 1 MB.
Please find the template below and prepare a pdf file with your name in the file name as "abstract_LastName_FirstName.pdf".
If the number of submissions exceeds the number of slots for contributed poster presentations, the presentors will be selected based on the abstracts.
Tips for poster presentations
1. The size of the poster board is 960 mm in width and 1800 mm in hight.
2. The recommended size of your poster is ISO A0 (841 mm × 1189 mm).
Registration
To attend the workshop, registration is required also for participants without presentation.
To attend the workshop with a presentation, please finish the registration and abstract submission by 2025/12/19 (Fri) for both oral and poster presentation (See above).
To attend the workshop without presentation, please finish the registration by 2026/1/12 (Mon) from the link below.
Please feel free to contact the organising committee if you have any questions.
Links to the registration page and the abstract template
Closed
Registration page Abstract template
Organiser
MEXT Joint Usage/Research Center Meiji University "Center for Mathematical Modeling and Applications" (CMMA))
Co-organiser
Contact
E-mail: active2026@googlegroups.com
錯覚の解明・創作のための諸アプローチとその応用
第20回錯覚ワークショップ
- 日時
- 2026年3月2日(月)、3日(火)
- 場所
- 明治大学中野キャンパス研究セミナー室3
組織委員長
杉原厚吉(明治大学)
組織委員
宮下芳明(明治大学)、北岡明佳(立命館大学)、一川誠(千葉大学)、星加民雄(錯視アーティスト)
谷中一寿(神奈川工科大学 名誉教授)、間瀬実郎(呉工業高等専門学校)、近藤信太郎(岐阜大学)、
大谷智子(大阪芸術大学)、須志田隆道(福知山公立大学)、山口智彦(明治大学)
概要
今年度の「錯覚ワークショップ」を明治大学中野キャンパスにおいて対面で開催します。今年度の中心テーマは「錯覚の解明・創作のための諸アプローチとその応用」です。「解明」と「創作」の両方の視点から錯覚について議論を深めることを目指して、錯覚に関する研究発表を広く募り、この分野の研究者の交流の場を提供します。ふるってご参加ください。
研究発表の募集
締め切りました
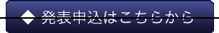
| スケジュール | |
| 2026年 1月13日(火) | 発表申し込みの締め切り |
| 1月19日(月) | 採否の連絡 |
| 2月9日(月) | アブストラクト(A4判1ページ)の締め切り |
| 3月2日(月)、3日(火) | 錯覚ワークショップ |
プログラム
| 3月2日(月) | |
|---|---|
| 13:00~13:30 | 谷中一寿(神奈川工科大学 名誉教授) |
| 13:30~14:00 | 間瀬実郎(呉工業高等専門学校) |
| 14:00~14:30 | 一川誠*、水野結夢(千葉大学) |
| 14:45~15:15 | 星加民雄(ホシカアートプロ) |
| 15:15~15:45 | 北岡明佳(立命館大学) |
| 16:00~17:00 | 招待講演 |
| 3月3日(火) | |
|---|---|
| 【午前の部】 | |
| 10:00~10:30 | 吉村莞太、井上雅世*(九州工業大学) |
| 10:30~11:00 | 須志田隆道*(福知山公立大学)、森将輝(早稲田大学)、近藤信太郎(岐阜大学) |
| 11:00~11:30 | 長谷川能三(甲南大学 非常勤講師) |
| 【午後の部】 | |
| 13:00~13:30 | 日高昇平*(北陸先端科学技術大学院大学)、鳥居拓馬(東京電機大学)、高橋康介(立命館大学) |
| 13:30~14:00 | 西本博之*、長崎太郎、永井口媛葉*、大成七菜美*(大阪産業大学) |
| 14:15~14:45 | 大谷智子*(大阪芸術大学)、丸谷和史(NTTコミュニケーション科学基礎研究所) |
| 14:45~15:15 | 杉原厚吉(明治大学) |
(*は複数著者の場合の講演者)
主催
明治大学「現象数理学」共同利用・共同研究拠点
共催
明治大学研究ブランディング事業 Math Ubiquitous 錯覚・錯視チーム
科研費挑戦的研究(萌芽)「視点を移動しても成立し続ける不可能立体の錯視要因の解明とその分類・体系化」
連絡先
第20回錯覚ワークショップ組織委員長 杉原厚吉
kokichis[a]meiji.ac.jp ([a]を@におき替えてください。)
高度な自動運転を実現するための数理の現状と課題
- 日時
- 2026年3月18日
- 開催方法
- オンライン開催
概要
日本独自のEnd-to-End(E2E)式自動運転技術はないとされている。このことは、経済安全保障の観点からも問題とされ、日本独自の「ほぼ自動で安全に走行できるAIモデルのロジック構築」が求められており、我々MIAD(明治大学先端科学ELSI研究所)の技術が一部で期待されている。
ここで、E2Eとは、入力(センサーデータ)から出力(車両の制御)までのすべてをAI(学習ベース)で実現する自動運転のアプローチである。MIADの高速・高精度の画像処理技術、因果の分かる独自の機械学習技術FQHNN、唯一リアルタイムで処理できるエネルギー最適制御EOCの組合せにより、認知、判断、制御 で圧倒的な優位性を有することが示されつつある。これらをベースに日本発のE2E技術に昇華させるために何をすべきか議論する。
組織委員
萩原一郎(明治大学)、木村 健(日産自動車(株))、藤井秀樹(東京大学)
古川 修(電動モビリティシステム専門職大学)、岡村 宏(芝浦工業大学)
ディアゴ・ルイス(明治大学)、安部博枝(明治大学)、西森 拓(明治大学)
Program
| 13:00~13:30 | 萩原一郎(明治大学) |
|---|---|
| 13:30~14:00 | 滝川桂一(明治大学) |
| 14:00~14:30 | 安部博枝((株)アビライト/明治大学) |
| 14:30~15:00 | ディアゴ・ルイス((株)インターローカス/明治大学) |
| 15:15~15:45 | 橋口真宜(エイチエム工学教育研究所/明治大学) |
| 15:45~16:15 | 岡村宏(芝浦工業大学/明治大学) |
| 16:15~17:00 | 総合討論及び閉会の辞 |
2025年度開催
研究集会型「独立開催タイプ」
| 2026年 3月6日 |
石森洋行 (国立環境研究所) |
|---|
ハイパースペクトルカメラを用いた廃棄物処理への数理科学からのアプローチに関する研究
- 日時
- 2026年3月6日(金)
- ハイブリッド開催
対面参加 明治大学中野キャンパス6階研究セミナー室3
オンライン参加
概要
NASAが開発したライン走査分光器を哺矢とするイメージング技術は、1970年代初頭以降質・量に桁違いの進化を遂げ、今日では環境・美術・考古・医・薬・理・農・工・食・軍事など様々な分野で活躍するハイパースペクトルカメラに結実している。本研究集会では、廃棄物処理という難問の解決を支援するハイパースペクトルカメラの活用技術と、そこに潜む数理的課題を議論する。
組織委員
石森洋行(国立環境研究所)、橋口真宜(計測エンジニアリングシステム(株))
中村健一(明治大学)、萩原一郎(明治大学)
Program
| 13:00~13:20 | 石森洋行(国立環境研究所) |
|---|---|
| 13:20~13:55(質疑10分含む) | 磯部友護(埼玉県環境科学国際センター) |
| 13:55~14:30(質疑10分含む) | 落合知(東京都環境科学研究所) |
| 14:30~14:40 | 休憩 |
| 14:40~15:15(質疑10分含む) | 杉本竜一(石坂産業株式会社) |
| 15:15~15:50(質疑10分含む) | 劉ジェシカ(グローバルアクシス) |
| 15:50~16:00 | 休憩 |
| 16:00~16:35(質疑10分含む) | 萩原一郎(明治大学) |
| 16:35~16:55 | 石森洋行(国立環境研究所) |
2025年度開催
共同研究型「経費支援タイプ」
| 2026年 2月27日 |
萩原 一郎 (明治大学) |
|---|
折紙構造・折紙式プリンター・扇構造の
工学的芸術的アプローチ
- 日時
- 2026年2月27日(金)
- ハイブリッド開催
対面参加 明治大学中野キャンパス 6階研究セミナー室3
概要
1)折畳音響室
2)不時着時においても乗員の安全を守る航空機構造
3)お洒落なヘルメットの衝撃特性
4)マルチパーパス切紙ハニカム構造
5)折畳み扇をベースとする新しい文化の創出
6)折紙工学援用細胞培養
これらのテーマでは、それぞれ共同研究者は異なるが、打ち破るべき解析技術の開発の主たるポイントは共通している。そこで上記の各共同研究者が集まり、共通する技術の開発を行う。
組織委員
萩原一郎(明治大学)、黒澤英孝(江戸伝統工芸・芸術文化保存振興協会)、吉村卓也(都立大学)
梶原逸朗(北海道大学)、奈良知惠(明治大学)、ディアゴ・ルイス((株)インターローカス)
戸倉直((株)トクラシミュレーションリサーチ)、西森拓(明治大学)
プログラム
| 2月27日(金) | |
|---|---|
| 10:00~10:10 | 萩原一郎(明治大学) |
| 10:10~10:35 | 山崎桂子(明治大学) |
| 10:35~11:20 | 崎谷明恵(明治大学) 阿部綾(明治大学) |
| 11:20~11:50 | 討議 |
| 13:00~13:25 | 佐々木淑恵(明治大学) |
| 13:25~13:50 | 萩原一郎(明治大学) |
| 13:50~14:20 | 討議 |
| 14:30~14:55 | 杉山有希子(明治大学) |
| 14:55~15:20 | ディアゴ・ルイス((株)インターローカス) |
| 15:20~15:50 | 討議 |
| 15:50~16:00 | 閉会の挨拶 |
2025年度開催
共同研究型「独立開催タイプ」
| 2026年 3月5日 |
銀河の力学構造の解明に向けての数理的研究 |
神部 勉 (明治大学) |
|---|
流体ゲージ理論の応用による、
銀河の力学構造の解明に向けての数理的研究
- 日時
- 2026年3月5日(木)
- ハイブリッド開催
対面参加 明治大学中野キャンパス6階研究セミナー室3
オンライン参加
概要
コーヒーカップにミルクを入れてかき混ぜると渦巻きが見える。台風の季節になると天気図に大きな渦巻が現れ、風速ベクトルの矢印がその回転方向を教えてくれる。これらは流体力学で説明できる。宇宙に目を向けてみよう。肉眼で見えるものは天の川銀河であるが、米国航空宇宙局NASA、欧州宇宙機関ESAあるいは合同で打ち上げられた宇宙望遠鏡による多くの銀河の写真がWebに掲載されている。ニュートンといった雑誌にもきれいな写真が掲載されている。驚くことに、台風の渦巻きとそっくりの銀河が多数あり、回転銀河と呼ばれている。光スペクトルの観測から回転銀河は250km/sといった高速で回転ししかも遠方でも回転が持続していることがわかっている。
ハンマー投げという競技がある。ワイヤーの先に錘をつけて回転をつけた後、手を放して飛距離を競う。手を放すまで、錘は選手を回転中心としてワイヤーを介した力とバランスをとるために自身の運動方向を変化させ回転運動をする。回転銀河は回転しておりそれを維持する力が必要である。そのような力は従来は重力のみであると考えられている。しかし既知の質量による重力では、観測された回転速度の半径方向の分布を説明できないことがわかり、ダークマターという謎の質量の存在が仮定された。
本集会は、数理科学の視点から、渦、回転銀河を検討し、ダークマターの謎解明に迫る。さらに宇宙の研究・開発への数理科学的アプローチを展望する。
組織委員
神部勉(明治大学/国際理論応用力学連合理事)、福本康秀(九州大学名誉教授)
中村健一(明治大学)、橋口真宜(明治大学)、関坂歩幹(明治大学)、白石允梓(広島市立大学)
山本宏子(理化学研究所)、萩原一郎(明治大学)、祖父江義明(東京大学名誉教授)
プログラム
| 3月5日(木) | |
|---|---|
| 13:00~13:10 | 萩原一郎(明治大学) |
| 13:10~13:40 | 神部勉(明治大学/元東大教授、元IUTAM日本代表) |
| 13:40~14:10 | 神部勉(明治大学/元東大教授、元IUTAM日本代表) |
| 14:10~14:30 | 橋口真宜(明治大学/国立環境研) |
| 14:30~15:00 | 関坂歩幹(明治大学) |
| 15:00~15:30 | 佐藤駿(東大理学部天文、物理学専攻出身、工学博士) |
| 15:30~17:00 | 総合討論及び閉会の辞 |